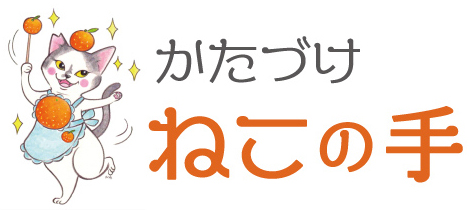パントリー収納の分け方と整理収納のコツ〜キッチン片付け事例〜|かたづけねこの手

皆さま、こんにちは。
京都市・JR山科駅を拠点に関西エリアで片付けサポートを行っている『かたづけ ねこの手』です。
朝晩の気温が下がり、秋らしさを感じる季節になりましたね。
体調を崩されないよう、どうぞご自愛くださいませ。
今回は、お客様宅の片付けサポートを通じて学びの多かったキッチン・パントリー収納の分け方についてご紹介します。
M様、この度は「かたづけねこの手」にご依頼くださり、誠にありがとうございました!
パントリー収納分け方のコツ〜消耗品ストック編〜
キッチンで使う消耗品ストックを多くお持ちの方は、とても多い印象です。
- ジップロック(大・中・小)
- 食品用ラップ
- アルミホイル・クッキングシート
- 輪ゴム・ゴム手袋
- スポンジなどのキッチン消耗品など
今回の収納スペースは、手前にゴミ箱があるため少し取りづらい位置。
そのため、「使用頻度が低いものを配置」しました。
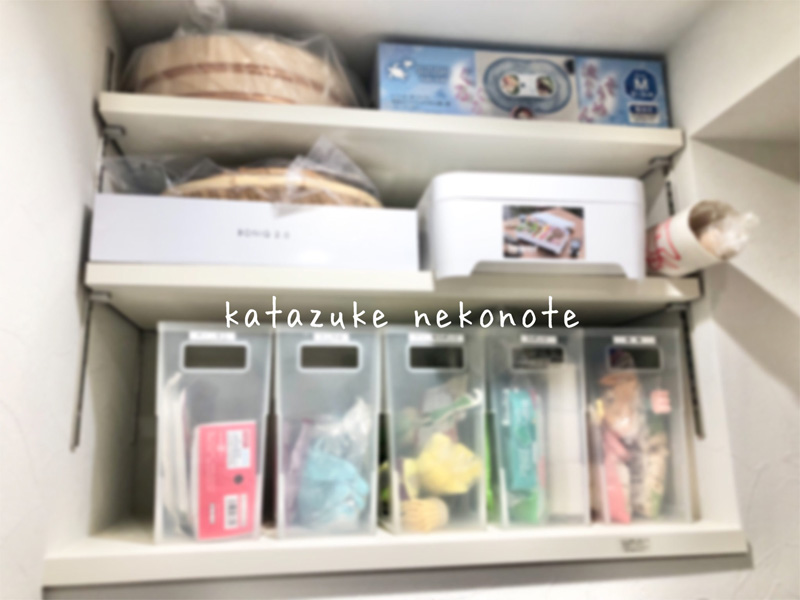
同じカテゴリーのアイテムをまとめることで、探す手間がなくなり、在庫管理も簡単になります。
引き出し1段目

引き出し2段目

パントリー収納分け方のコツ〜食品ストック編〜
上段には、ジップロックやラップ、アルミホイルなどのストックで軽いアイテムを収納。
下段には、よく使う食品(味噌汁・スープ・グラノーラなど)を取っ手付きケースに入れ、サッと取り出せるようにしました。

上段の奥には紙皿・紙コップ・割り箸・予備のおかずカップなどを収納。
使用頻度が低いものは、「高い位置・奥側」が基本です。
下段の取っ手付きケースには、タッパーやワンちゃんのフードを収納しました。
「使う場所の近く」に「使うモノ」を置く。これが片付けを続けるコツです。

食品ストックの分類ポイント
食品はカテゴリー別に分けることで、在庫が一目で把握できます。
- インスタント食品
- 調味料・薬味
- ふりかけ
- お茶・紅茶・コーヒー
- お菓子など
よく食べる・購入頻度が高い食品は手前や取り出しやすい位置に、
重いモノは下に配置すると安全です。

「お店の陳列のようにカテゴリーごとに並べる」ことを意識すると、
視覚的にわかりやすく、在庫管理がしやすくなります。
片付くおうちを作るための整理収納の基本
片付けの基本は、まず「モノの整理」から。
「使っているモノ」を収納し、「使っていないモノ」はいったん保留ボックスへ。
食品は賞味期限があるため「捨てどき」がわかりやすいですが、
それ以外のモノは「まだ使える」「もったいない」と思って手放せないことも多いですよね。
そんなときは、モノにも“鮮度”や“旬”があると考えてみましょう。
今の自分に合わないモノは「ありがとう」と手放すと、心もスペースもすっきりします。
収納の3つのコツ
- 適正量:収納スペースと持ち物の量をバランスよく
- 使いやすさ:取り出しやすく戻しやすい仕組み作り
- 見える化:一目でわかる収納を意識
これらを意識するだけで、毎日のキッチンがもっと快適になります。
最後に〜片付けは「思いやりのかたち」〜
M様、この度は「かたづけねこの手」にご依頼いただき、誠にありがとうございました。
ご家族が気持ちよく使えるキッチンづくりのお手伝いができて、とても嬉しかったです。
片付けは、暮らしを整えるだけでなく、
家族を想う優しさや、自分を大切にする心にもつながります。
皆さまのおうちにも、「片付けが続く仕組み」と「笑顔が増える空間」が広がりますように。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。